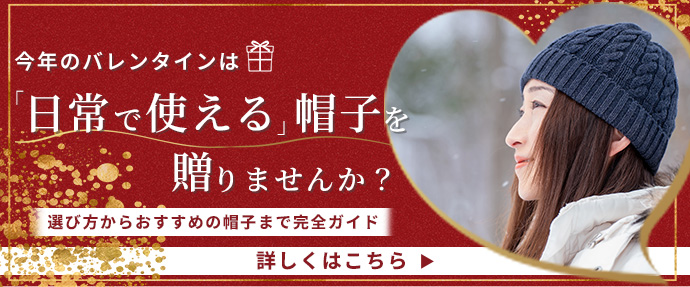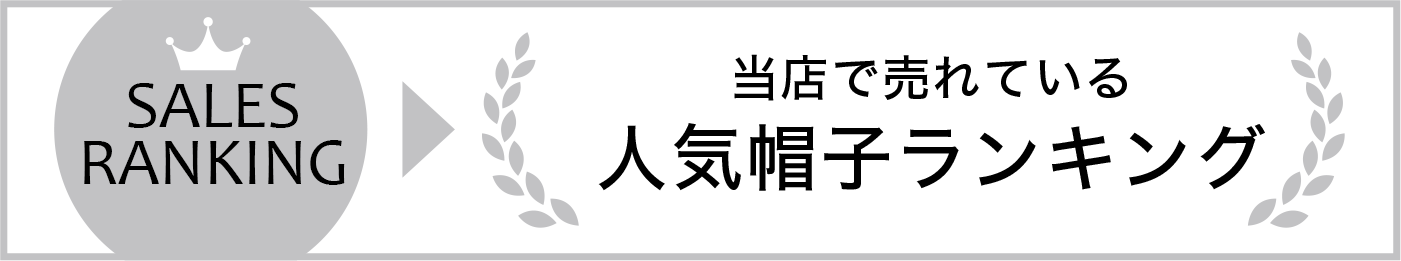サイズ・色・帽子ブランドの種類が春夏秋冬で豊富な老舗のメンズ、レディース帽子通販専門店ライオンドウです。今回のブログは、「帽子とは?帽子の目的や効果、歴史、その種類や名称について」について書きたいと思います。
帽子とは何か?
帽子とは、一般的には頭にかぶるものとして定義されています。その目的は実にさまざまです。帽子は、ファッションアイテムをはじめとし、制帽(制服、ユニフォームの一部)であったり、身分をあらわす象徴であったり、日よけや防寒、頭部を守るための機能的なものであったりとその目的も多岐にわたります。現在でも具体的に、ストリートファッションのバケットハット、飲食店の制帽のハンチング、リゾート地での日焼け防止の麦わら帽、マラソンでかぶるキャップなどそのシーンや用途はいろいろです。

帽子をかぶる目的とは?
帽子をかぶる目的とは、暑さ、寒さなど気温の変化や砂やほこりから身を守るため、権威の象徴や役割をわかりやすくするためです。下記はその主な例です。
- 日除けなど日光の紫外線から身を守るため(キャップやつば広のハットなどの帽子)
- 雪や寒さから身を守るため(耳当て付きのキャップやロシア帽などの帽子)
- 雨や風などから身を守るため(レインハットや登山用のアウトドアハットなどの帽子)
- 花粉やほこりなどから身を守るため(クリアサンバイザーなどの帽子)
- スポーツ選手が競技時に頭を保護したりチームをわかりやすくするため(野球選手のベースボールキャップなどの帽子)
- スタッフや従業員としてわかりやすくするため(飲食店や警備員、清掃員などの制帽、ユニフォームなどの帽子)
- 象徴的なファッションアイテムとして自分を魅力的にみせるため(芸能人がいつもかぶっているアイコニックなキャップなどの帽子)
帽子をかぶる効果やメリットとは?
帽子をかぶる効果やメリットとは、暑さや寒さなどから身を守ることできたり、わかりやすく役割を伝えることなどがあります。具体的な帽子をかぶる効果やメリットは、例えば帽子をかぶることで、日光が直接頭に当たる場合に比べて約10度温度が下がると言われています。帽子をかぶることで熱中症の防止になります。サウナハットもかぶることで頭部が高温になりのぼせるのを防止するといわれています。帽子をかぶることで頭部を守り、頭部を守ることで身体全体を守ることにつながっていくのです。
帽子の歴史について
日本の帽子の歴史
日本の帽子の歴史は、どこから始まったのか正確なところはわからないものの、有名なものでは烏帽子などが平安時代からかぶられていたとされています。その後は笠などをかぶる文化があったものの、大きく変化したのは明治以降とされます。断髪令でザンギリ頭になってから、西洋の帽子が輸入され、また日本でもつくられるようになってきます。「帽子をかぶらないのはありえない」と言われるくらい、帽子をかぶる割合が9割を超えた時期もあったようで、帽子をかぶることが紳士のエチケット・マナーとなっていました。昭和初期までは非常に帽子をかぶる人が多かったようですが、戦後から徐々にその人数は落ち着いてくるようになってきました。
日本の有名帽子ブランド
平成にCA4LA(カシラ)やOVERRIDE(オーバーライド)といったブランドが火付け役となって帽子ブームが起こり、現在では個性を表現するファッションアイテムのひとつとして定着しつつあるようです。
世界の帽子の歴史
世界でも宗教的なシーンや軍隊の帽子などさまざまなシーンで帽子はかぶられてきました。帽子の発祥は、古代ギリシャだともいわれています。王冠などもあるように、権威の象徴としてかぶられるようなものもありましたが、現在の帽子につながるもととなったのは18世紀から19世紀にかぶられていたシルクハットなどが原型となっています。ハットなど正装としてかぶられていましたが、狩猟用に英国(イギリス)でハンチングがつくれるようになり、現在のキャップへとつながっていきます。
世界の有名帽子ブランド
現在世界最古として、最も古い帽子屋(帽子専門店)とされているのが、1676年創業のジェームスロック&カンパニー・ハッターズ(James Lock & Co. Hatters)です。当時、貴族が被る紳士(男性)用の帽子として定着していたボーラーハットで有名になりました。1857年にはボルサリーノ(Borsalino)がソフトハットと言われる中折れ帽をつくったことでハットに大きな流れができました。1920年にはニューエラ(NEW ERA)がアメリカで創業され、メジャーリーグの公式サプライヤーになり、ベースボールキャップで有名になりました。
帽子の種類について
帽子の種類は本当にさまざまですが、大きくわけるといくつかのかたちに分類できそうです。大きくわけると中折れ帽のようなツバがついたハット、一部にツバがついたキャップ、ハンチング、キャスケット。そしてベレー帽やニット帽といったツバのないかたちです。あとはツバのかたちやトップのかたちなどでそれぞれの名前がついています。
ハット
ハットは、主にツバ(ひさし、ブリム)がクラウン(頭部)をぐるりと一周ついているものを指します。素材やかたちによって呼ばれ方は異なります。
中折れ帽(フェルトハット・ソフトハット)
中折れ帽は、中折れハットなどと呼ばれ、帽子の頭部がくぼんで持ちやすいようになったハットを指します。(実際に頭部のへこみをつまむと帽子は傷みやすいのでツバを持ちましょう)フェルトやウールの素材を使用することも多いので、フェルトハットやウールハットなどといった呼び方もします。
title => フェルトハット/THE FELT HAT
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/09091439_631ad19780593.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
5000円以上,
ホワイト系,
ベージュ系,
ブラウン系,
グレー系,
ブラック系,
グリーン・カーキ系,
ブルー・ネイビー系,
レッド・ワイン系,
秋・冬,
フェルト,
センスオブグレース(Sense of Grace、グレース、grace)
price => 5060
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 普通サイズの定番フェルトハット。シンプルで使いこなしのできるハットはこの冬も必須アイテムです。幅広いコーデに対応できるので、気分を変えて色違いで持つのもオススメ。スベリの裏でサイズ調整も可能です。
url => https://lion-do.jp/products/detail/414
普通サイズの定番フェルトハット。シンプルで使いこなしのできるハットはこの冬も必須アイテムです。幅広いコーデに対応できるの…
麦わら帽子・ストローハット・ペーパーハット
麦わら帽子は、ストローハットともいわれ、主に天然草を使用した春夏用のハットを指します。近年は紙繊維や天然草に似たポリエステルなどの化学繊維でつくられることもあり、ペーパーハットなどといった呼び方もします。かたちは中折れ帽とほぼ同じつくりのことが多いです。
title => ブレイドハット ウォッシュ ペーパーハット ストローハット 洗濯 メンズ レディース 春夏
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/FST541H.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
〜60cm,
〜61cm,
ホワイト系,
ブラウン系,
グレー系,
ブラック系,
ブルー・ネイビー系,
春・夏,
天然素材・ペーパー,
センスオブグレース(Sense of Grace、グレース、grace)
price => 4730
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 洗濯機で洗える春夏向け中折れハットです。ベルトと本体のカラーバランスが絶妙なスタイリッシュなデザイン。後ろのつばが上がっている、かぶりやすいベーシックなシルエットです。水に強いポリエステル・ブレードを使用しているため、手洗いはもちろん、洗濯
url => https://lion-do.jp/products/detail/2392
洗濯機で洗える春夏向け中折れハットです。ベルトと本体のカラーバランスが絶妙なスタイリッシュなデザイン。後ろのつばが上がっ…
ボーラーハット
ボーラーハットは、トップが丸いハットです。コーク氏が提案したことからつくられたハットということでコークハットとも呼ばれることがあります。
title => フォーク・ボーラーハット/FORK BOWLER HAT
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/TH140.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
5000円以上,
グレー系,
ブラック系,
グリーン・カーキ系,
ブルー・ネイビー系,
秋・冬,
フェルト,
センスオブグレース(Sense of Grace、グレース、grace)
price => 6160
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => ベーシックなスタイルのフェルト・ボーラーハット。トップに丸みがあり、つばが全体にクルリと上を向いているのが特徴です。リボンとつばのパイピングが同色なので、上品でしっくり落ち着いた印象。スベリの裏でサイズ調整も可能です。
url => https://lion-do.jp/products/detail/412
ベーシックなスタイルのフェルト・ボーラーハット。トップに丸みがあり、つばが全体にクルリと上を向いているのが特徴です。リボ…
カンカン帽(カンカンハット)
カンカン帽は、英語ではボーター、フランス語ではキャノチェとも呼ばれ、トップが平らで円筒形、比較的つばの短いつばがついた帽子です。叩くとカンカンと音がすることから名前がついています。素材は主に麦わらがメインでしたが、近年ではさまざま素材が使用されています。
title => MOYU ボーターハット カンカン帽 メンズ レディース 春 夏
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/EST311F.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜55cm,
〜56cm,
〜57cm,
〜4999円,
ホワイト系,
ベージュ系,
春・夏,
天然素材・ペーパー,
センスオブグレース(Sense of Grace、グレース、grace)
price => 4950
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 細めのペーパーブレードを使ったカンカン帽子。シンプルリボンの組み合わせが大人っぽい仕上がりになっています。コーデに合わせやすく、被るだけでオシャレ度が増すハットです。サイズ55cm~57cm推奨。スベリの裏でサイズ調整ができます。帽子の大き
url => https://lion-do.jp/products/detail/2176
細めのペーパーブレードを使ったカンカン帽子。シンプルリボンの組み合わせが大人っぽい仕上がりになっています。コーデに合わせ…
メトロハット
メトロハットとは、主にトップが6パネルで構成されていて丸みを帯びたサファリハットになります。幼稚園や保育園などの制帽として採用されることもある多いかたちです。
title => ニューエラ エクスプローラー/NEW ERA EXPLORER
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/0706130628_6869f644c4a85.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
〜60cm,
〜61cm,
〜62cm,
62cm以上,
〜4999円,
ブラック系,
グリーン・カーキ系,
その他,
春・夏,
秋・冬,
オールシーズン,
綿,
ニューエラ (NEW ERA),
父の日
price => 5060
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 59FIFTYのクラウン部分のシルエットをハットタイプにアレンジした帽子。サイズ展開が豊富で大きいサイズから小さいサイズまで対応。裏地は蒸れないようにメッシュ生地になっており、通気性も考慮されている。
url => https://lion-do.jp/products/detail/46
59FIFTYのクラウン部分のシルエットをハットタイプにアレンジした帽子。サイズ展開が豊富で大きいサイズから小さいサイズ…
サファリハット・バケットハット
サファリハットは、トップが平でつばのついたハットになります。厳密にはサファリハットは探検帽としてつくられたもので、バケットハットは、バケツをひっくり返したような形状のハットを示しますが、かたちが似ているので同じような呼ばれ方をします。
title => ラコステ サファリハット バケットハット L3981
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/L3981.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜58cm,
〜59cm,
5000円以上,
ホワイト系,
ベージュ系,
ブラック系,
ブルー・ネイビー系,
オールシーズン,
綿,
ラコステ (LACOSTE),
日本
price => 7920
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 綿100%のシンプルで幅広い層にかぶっていただけるサファリハットです。メンズ・レディース兼用で年中通してかぶれます。サイズは58.5cmでワンサイズです。平置き時は31cm×27cm×11cmです。色はベージュ、モスグリーン(カーキ)、ネイ
url => https://lion-do.jp/products/detail/2450
綿100%のシンプルで幅広い層にかぶっていただけるサファリハットです。メンズ・レディース兼用で年中通してかぶれます。サイ…
title => ニューエラ バケットハット 01 newera バケハ メンズ レディース
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/0706125608_6869f3d80bc75.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
〜60cm,
〜61cm,
〜4999円,
ホワイト系,
ブラック系,
ブルー・ネイビー系,
オールシーズン,
綿,
ニューエラ (NEW ERA)
price => 4950
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => NEW ERA(ニューエラ)の定番のバケツをひっくり返したようなシルエットが特徴のアウトドア系のハット。シンプルなつくりで折りたたんで持ち運んだりできます。もちろんタウンユースとしても使えていろいろなコーディネートにあわせやすい帽子です。メ
url => https://lion-do.jp/products/detail/2205
NEW ERA(ニューエラ)の定番のバケツをひっくり返したようなシルエットが特徴のアウトドア系のハット。シンプルなつくり…
ポークパイハット
ポークパイハットは、トップが平らで円筒形になっていて、つばが短く、ポークパイというパイに似ているから名前がつけられた帽子になります。カンカン帽にも似た見た目になりますが、素材の違いから呼ばれ方が異なります。(厳密な定義はありません)
title => カンゴール・バンブーモーブレイ・ポークパイハット/KANGOL
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/185-169212-.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
〜60cm,
〜61cm,
5000円以上,
グレー系,
ブラック系,
春・夏,
カンゴール (KANGOL)
price => 10230
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 竹繊維を使用した春夏向けのカンゴール・ポークパイハット。KANGOLの定番となったバンブーシリーズ。柔らかく、しなやかな質感のシンプルなポークパイハットです。 竹素材はサラッとした手触りで、天然の抗菌性や高い吸湿性を特徴とする快適素材。サイ
url => https://lion-do.jp/products/detail/1676
竹繊維を使用した春夏向けのカンゴール・ポークパイハット。KANGOLの定番となったバンブーシリーズ。柔らかく、しなやかな…
シルクハット
シルクハットは、トップが高く、トップハットとも言われます。ネタが隠しやすく、マジシャンなどが愛用したハットです。主に社交場などでかぶられていた歴史があります。
title => ベイリー・ロールブリム・シルクハット・ICE /Bailey
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/168-154208.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハット,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
〜60cm,
〜61cm,
5000円以上,
ブラック系,
秋・冬,
フェルト,
del_ベイリー (Bailey)
price => 19800
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 根強い人気のベイリー・シルクハット。別名トップハット。クラウンは14cmと程よい高さで、フォーマルはもちろんタウンユースにも使えるおしゃれアイテム。M(57.5cm)、L(59cm)、XL(60.5cm)。つば4.5cm。羽根付き。アメリカ
url => https://lion-do.jp/products/detail/892
根強い人気のベイリー・シルクハット。別名トップハット。クラウンは14cmと程よい高さで、フォーマルはもちろんタウンユース…
テンガロンハット・ウエスタンハット・カウボーイハット
テンガロンハットは、テンガロン(=10ガロン)の水が入ることからその名前をつけられたという説もあるハットです。ウエスタンハットは、西部開拓時代に被られていたことからついた名前の帽子です。カウボーイハットは、メキシコのカウボーイがかぶっていたことからついた名前の帽子です。テンガロンハットとウエスタンハットとカウボーイハットの違いは、明確にはトップの形状やつばの反り具合や形状で異なりますが、日本では実際のところ大きな差はなく、ツバの広くて大きな中折れ帽を指していることが多いです。
チューリップハット
チューリップハットは、主に6パネルでつくられ裾の部分は広がった帽子です。昔ノッポさんがかぶっていたことから印象に強いかたちです。
title => チューリップハット レディース 婦人 ladys ウィメンズ ベージュ 黒
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/GM117.jpg
cat =>
レディース,
ハット,
〜57cm,
〜2999円,
ブラウン系,
ブラック系,
春・夏,
綿,
その他のブランド
price => 2750
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => コットン100%のチューリップハット。トップが平らなのでノッポさんの帽子のようなかたちではなく、バケットハットに近いかたちになりますが、ツバの部分に腰といわれる切り替え部分がないのでストンとすっきりした印象です。すその部分はロックミシンがか
url => https://lion-do.jp/products/detail/2370
コットン100%のチューリップハット。トップが平らなのでノッポさんの帽子のようなかたちではなく、バケットハットに近いかた…
キャップ
キャップは、主にクラウン(頭部)に対して前方にツバ(ひさし、ブリム)のついた帽子です。ツバ(ひさし、ブリム)がついているので、日よけなどに良い帽子です。またハットにくらべて視野も広いのでスポーティーな場面でも活躍します。
ベースボールキャップ(野球帽)
ベースボールキャップは、主に6パネルのトップでつくられたつば付きの帽子です。野球をするときによくかぶられるので、ベースボールキャップ、野球帽などとよばれています。ベースボールキャップで有名なブランドはニューエラ(NEW ERA)になります。
title => ニューエラ・キャップ・ナイントゥエンティー・クロスストラップ/9TWENTY/NEW ERA
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/0706125414_6869f3660184a.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
キャップ,
〜55cm,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜4999円,
ホワイト系,
グレー系,
ブラック系,
グリーン・カーキ系,
ブルー・ネイビー系,
オールシーズン,
綿,
ニューエラ (NEW ERA)
price => 4620
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 6枚パネルで構成された浅めのかぶりのベースボールキャップ。素材にウォッシュドコットンを採用。バックには布ベルトのアジャスター(クロスストラップ)を使用し、シンプルでカジュアルなテイストに仕上がっている。フロントに芯が無いので柔らかなフィット
url => https://lion-do.jp/products/detail/769
6枚パネルで構成された浅めのかぶりのベースボールキャップ。素材にウォッシュドコットンを採用。バックには布ベルトのアジャス…
ワークキャップ
ワークキャップとは、主に仕事や作業をするときにかぶられるキャップです。トップが平らであるのが特徴になります。
title => マイナーキャップ/MINER CAP
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/06071552_5392b694ec0ea.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
キャップ,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
〜60cm,
〜61cm,
〜62cm,
〜3999円,
ベージュ系,
ブラック系,
グリーン・カーキ系,
ブルー・ネイビー系,
春・夏,
秋・冬,
オールシーズン,
綿,
センスオブグレース(Sense of Grace、グレース、grace)
price => 3960
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => しっかりとしたキャンバス生地でオールシーズン使える定番ワークキャップ。バックのタグとベルトがレトロで、ウォッシュドのような風合いの生地がユーズド感を漂わせている。カジュアルシーンにはかかせないアイテム。※ユーズド加工されているので最初から使
url => https://lion-do.jp/products/detail/95
しっかりとしたキャンバス生地でオールシーズン使える定番ワークキャップ。バックのタグとベルトがレトロで、ウォッシュドのよう…
ワッチ・ビーニー(ニット帽)
ワッチ・ビーニーとは、主にニット素材でできた帽子です。糸を編み上げてつくるもの、また糸を編み上げた後に縫製でかたちをつくるものなどがあります。
ワッチ・ビーニー
ワッチ・ビーニーとは、一般的なニット帽のことです。つばがなく、伸縮性があります。編み方によって伸縮性などが変化します。
title => ワッフルワッチ・グラフ3
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/ASW201U.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ニット帽,
〜57cm,
〜58cm,
〜59cm,
〜60cm,
〜61cm,
〜62cm,
〜2999円,
グレー系,
ブラック系,
ブルー・ネイビー系,
春・夏,
秋・冬,
オールシーズン,
綿,
センスオブグレース(Sense of Grace、グレース、grace)
price => 3190
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => たっぷりしたシルエットの深めにゆったりかぶれるワッフルワッチ。主にコットン素材を使用してあるので、肌触りもよくサラリとした質感です。
幅広いサイズに対応できるワッフル生地のビッグワッチは伸縮性もあり、頭まわりの大きな方にもオススメ。
(5
url => https://lion-do.jp/products/detail/1173
たっぷりしたシルエットの深めにゆったりかぶれるワッフルワッチ。主にコットン素材を使用してあるので、肌触りもよくサラリとし…
ハンチング
ハンチングとは、イギリスで発祥した狩猟用としてつくられた帽子のことです。つばが前に出ているのが特徴です。
title => ラコステ・コットンハンチングL1130/LACOSTE
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/1222160840_658535f83b7c0.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
ハンチング,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
5000円以上,
ベージュ系,
ブラック系,
オールシーズン,
綿,
ラコステ (LACOSTE),
日本
price => 9350
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => ラコステの綿100%ハンチング。上品な光沢とハリのあるツイル素材を使用した、きちんと感のあるハンチングです。単色でシンプルなデザインなので、幅広いコーデにおすすめ。サイズ56cm~58cm推奨。スベリの裏でサイズ調整できます。オールシーズン
url => https://lion-do.jp/products/detail/1845
ラコステの綿100%ハンチング。上品な光沢とハリのあるツイル素材を使用した、きちんと感のあるハンチングです。単色でシンプ…
キャスケット
キャスケットとは、ハンチングがフランスで派生した帽子になります。トップが大きいのが特徴ですが、ハンチング帽との違いがあまりない場合もあります。
title => T・HALキャスケット
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/BSA202U-.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
キャスケット,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜3999円,
ホワイト系,
ベージュ系,
グレー系,
ブラック系,
ブルー・ネイビー系,
春・夏,
綿,
麻,
センスオブグレース(Sense of Grace、グレース、grace)
price => 3960
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 上から見るとエスカルゴの様に見える8枚ハギのキャスケット。シンプルだからこそ、クラウンの形にこだわって、角が立ちにくく、きれいなラインを出すためにパネルの一枚一枚を緩やかなカーブを描くようにカットし縫い合わせています。麻綿のラフな素材感は春
url => https://lion-do.jp/products/detail/1957
上から見るとエスカルゴの様に見える8枚ハギのキャスケット。シンプルだからこそ、クラウンの形にこだわって、角が立ちにくく、…
ベレー帽
ベレー帽は、主に丸みのあり、つばがないかたちの帽子です。
title => フラミンゴ バスクウールベレー/FLAMINGO BASQUE WOOL BERET
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/240-1001.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
キッズ,
ベレー帽,
〜54cm,
〜55cm,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜3999円,
ベージュ系,
ブラウン系,
グレー系,
ブラック系,
グリーン・カーキ系,
ブルー・ネイビー系,
レッド・ワイン系,
秋・冬,
フェルト,
その他のブランド,
日本,
敬老の日
price => 4950
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => 良質なメリノウール100%のウールフェルトを使用したかぶりやすいシンプルな純国産のバスクベレー帽です。フラミンゴのマークがトレードマークとなっており、羊毛の編立から染色、成型、縫製、検品までの全工程を半世紀以上一貫して生産している長年の技術
url => https://lion-do.jp/products/detail/190
良質なメリノウール100%のウールフェルトを使用したかぶりやすいシンプルな純国産のバスクベレー帽です。フラミンゴのマーク…
サンバイザー
サンバイザーは、日除けを目的としてかぶられることの多い帽子です。スポーツの場面などで活躍します。
title => コンバース 2WAY ジョッキー サンバイザー 黒 ブラック 日よけ 日焼け防止 紫外線対策
image => https://lion-do.jp/html/upload/save_image/0324124326_67e0d4de35fd3.jpg
cat =>
メンズ,
レディース,
その他の帽子,
〜56cm,
〜57cm,
〜58cm,
〜4999円,
ブラック系,
春・夏,
オールシーズン,
その他のブランド,
UV・日よけ,
母の日
price => 4290
type => og:product
site_name => 帽子専門店LION-DO|メンズ・レディース帽子通販本店
description => コンバース(CONVERSE)のジョッキー・サンバイザー。フロント部分にたたんであるメッシュ布を広げると通気性の良いジョッキーになり、バイザーとの2WAYでかぶって頂けます。額に当たるスベリの幅は約4.5cmと通常より幅広になっており、安定
url => https://lion-do.jp/products/detail/2751
コンバース(CONVERSE)のジョッキー・サンバイザー。フロント部分にたたんであるメッシュ布を広げると通気性の良いジョ…
パイロット(飛行帽)・ウシャンカ(ロシア帽)
パイロット(飛行帽)は、もともと飛行機乗りのための帽子で、耳当て部分がついていて防寒性が高い帽子です。ウシャンカ(ロシア帽)は、ロシアでかぶられることが多い帽子で防寒性があります。銀河鉄道999で登場したメーテルがかぶっていた帽子に似ていることからメーテル帽とも呼ばれます。パイロット(飛行帽)とウシャンカ(ロシア帽)の違いは、日本ではあまり明確にありません。
帽子の名称、呼び方について
帽子の各部分を示す言葉としてそれぞれ専門の名称や呼び方があります。一般的に使用するものから聞きなれないものまであります。
- つば=帽子のひさしの部分。ブリムとも言います。キャップやハットについている日よけの部分です。
- クラウン=帽子のボディになる部分。いわゆる頭を覆いかぶさっている部分で王冠であるクラウンから来ていると思われます。
- 天ボタン=キャップの一番てっぺんの部分にある丸いボタンです。縫い目を補強したり、仕上がりがきれいに見えるように取り付けられています。まれに天ボタンがないデザインのものもあります。
- コシ(腰)=ハットなどにあるブリムの上(クラウンの下)にあるクラウンを一周巻いた布地の部分になります。主には仕上がりの良さ(デザイン的な部分)と補強のような役割になります。あるとのっぺりとした印象でなく立体的なデザインとなります。
- シコロ=ニット帽の折り返しの部分。ニット帽にボリューム感が出ます。
- 梵天(ぼんてん)=ポンポンニットのてっぺんの丸い部分。
- スベリ・ビン革=帽子の内側の額やおでこなどが当たるテープ部分。こちらがあることでサイズ感が安定し、汗を吸い取るので帽子の生地が傷みにくいといった利点があります。吸湿速乾性の素材を用いることもあります。スウェットバンドともいいます。
- 巻(マキ)=フェルトハットなどのリボンの部分。グログランテープなどが用いられます。
- 渡し(わたし)=巻のつなぎ目を隠すために主に使われる布地の部分です。
- ピンチ=ハットのつまみとなる部分。先端のへこみ。こちらを最初に考案したのがイタリアのボルサリーノ社ともいわれています。
- ハトメ=帽子のクラウン(頭部)につけられた穴で、帽子をかぶったときのふくらみを抑え、通気性をよくするためにあります。

キャップの後ろやハットの横にある帽子の穴は何のためにあるのか?
キャップの後ろやハットの横にある帽子の穴は、ハトメや菊穴などと呼ばれ、本来は帽子をかぶることによって空気が入り込んでしまい、帽子が膨らんでしまうことを避けるための穴でした。汗を逃がしたり蒸れにくくするためにも効果的なために通気口の役割として帽子についています。
帽子のシーズン(季節)について
帽子には、それぞれの素材によってかぶるシーズン(季節)の目安があります。
- オールシーズン可・・・年中通じてかぶれる綿素材などが中心です。
- 主に春夏向け・・・麻や絹などの天然素材や薄手のもの、風通しの良いものなどが中心です。
- 主に秋冬向け・・・フェルト素材やウール素材、厚手のものなどが中心です。
上記のものは(夏物のサマーウールなどあるので)必ずしも絶対的なものではありませんが、一つの目安としてご参考ください。
帽子のお手入れについて
帽子のお手入れ方法、洗濯の仕方
帽子を購入したあとは、お手入れやメンテナンス、しっかりとした洗濯や保管をすることで帽子が長持ちします。
-
洗濯できない帽子の場合
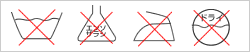
- 基本的に洗濯ができません。
- 帽子の汚れは額から出る汗で汚れることが多いので、額や頭と接する場所を、かたくしぼった濡れタオルなどでこまめにふき取ってあげることが大事です。あとは市販の消臭除菌スプレーなどで対応をします。(目立たない部分で試してください。)軽微な染みなどでない汚れであれば消しゴムで落ちる場合もあります。こすりすぎは生地を傷めますので角などでそっとこすってみて下さい。ファンデーションや強い汚れの場合はベンジンなどでとることもできますが、変色などをおこす可能性があるためにあまりオススメではありません。
-
| 洗濯できない主な素材 |
| 綿(※)、麻(※)、絹(※)、天然素材(ストロー、ラフィア、シゾール、アバカ、バオ、パナマ)、ペーパー、ウール(※)、アンゴラ(※)、モヘア(※)、カシミア(※)、アルパカ(※)、ファー、レザー、ポリエステル(※)、アクリル(※)、ポリウレタン、レーヨン(※) |
| 洗濯できない主な帽子 |
| ハンチング(※)、キャスケット(※)、ニット帽(※)、キャップ(※)、ストローハット、中折れハット、サファリハット(※)、ポークパイハット、ベレー帽(※)、サンバイザー(※) |
※上記はあくまで目安です。正しくはお帽子の洗濯表示をご参照ください。
手洗い可能な帽子の場合
-

汚れが目立つ箇所はえりそで用部分洗い剤などをつけ、汗ジミなどがある場合は液体酸素系漂白剤か、しみ用の部分洗い剤をつけます。30℃くらいのぬるま湯か水につけ、押し洗うようにそっと手で洗濯します。
(※洗濯機を使用すると型崩れなどをおこしますのでお控え下さい。)洗い終わったら水ですすいだ後に、タオル等で水気をとり、自然乾燥・陰干しします。このときにシワを伸ばし、帽子の中にタオルや調理用ザルなどを入れて形を整えて乾燥させます。きちんと整えて乾燥させないと縮みなどの原因にもなります。(※洗濯機での脱水、天日干しは型崩れなどをおこしますのでお控え下さい。)
-
-
| 手洗い可能な主な素材 |
| 綿(※)、絹(※)、ウール(※)、アンゴラ(※)、モヘア(※)、カシミア(※)、アルパカ(※)、ポリエステル(※)、アクリル(※) |
| 手洗い可能な主な帽子 |
| ハンチング(※)、キャスケット(※)、ニット帽(※)、キャップ(※)、サファリハット(※)、ベレー帽(※)、サンバイザー(※) |
※上記はあくまで目安です。正しくはお帽子の洗濯表示をご参照ください。
ドライクリーニング可能な帽子の場合
-
-
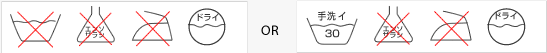
お近くのクリーニング専門店でご相談されることをオススメします。
お店によっては、フェルトなどの帽子でもクリーニング後に型入れできる店などもあるようです。
-
| ドライクリーニング可能な主な素材 |
| 麻(※)、絹(※)ウール(※)、アンゴラ(※)、モヘア(※)、カシミア(※)、アルパカ(※)、ポリエステル(※)、アクリル(※)、レーヨン(※) |
| ドライクリーニング可能な主な帽子 |
| ハンチング(※)、キャスケット(※)、ニット帽(※)、ベレー帽(※) |
※上記はあくまで目安です。正しくはお帽子の洗濯表示をご参照ください。
帽子の保管方法について
帽子は直射日光、湿気や水気に弱いものが多いので、日の当たらない風通しの良い場所に保管されるのが良いと思います。箱に入れる場合、ウールや天然素材のものは防虫剤を忘れずにお入れ下さい。帽子の中にクッションや紙を入れておくと、型くずれの防止にもなります。
帽子の寿命について
帽子の寿命は、一般的には3から5年程度と言われています。もちろんかぶる頻度やこまめなお手入れ、正しい帽子の収納、保管方法によっても異なってきます。
帽子の数え方について
帽子の数え方は、基本的に「個」の単位を使用します。1個、2個、3個・・・(または一つ、二つ、三つ・・・)と通常の個数を数える時と同じです。ニット帽などの場合は1枚、2枚と「枚」の単位を使用する場合もあります。また店頭での販売の場合は1点、2点と「点」の単位を使用する場合もあります。
帽子をかぶるを漢字で書くと何?
帽子をかぶるを漢字で書くと「帽子を被る」になります。
帽子をかぶるの反対は何?
帽子をかぶるの反対は、「帽子を脱ぐ」です。
帽子をかぶるを英語でいうと何?
帽子をかぶるを英語でいうと「put on 」または「wear」などになります。
帽子を含む四字熟語は何?
帽子を含む四字熟語には以下のようなものがあります。
- 「烏帽子親(えぼしおや)」=武家の元服式の際に烏帽子をかぶらせ、烏帽子名をつける人のこと。
- 「弊衣破帽(へいいはぼう)」=破れてぼろぼろの衣服や帽子のこと。
似合う帽子の選び方について
帽子をかぶる際には、似合う帽子を選ぶコツというのがあります。主には帽子のサイズと顔の輪郭など顔のかたちにあわせた選び方です。
似合う帽子のかぶり方について
帽子を選んだあとは、それぞれのベストのかぶり方をすることでより似合う帽子となります。主に角度や向き、深さがポイントとなってきます。
帽子のブランドについて
帽子にもブランドがあります。世界最古の帽子屋といわれているのは1676年に設立されたジェームス・ロック・アンド・カンパニー・ハッターズ(James Lock & Co. Hatters)といわれています。各メーカーによってそれぞれの特色がありますので、比較してみるのも面白いでしょう。



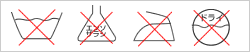

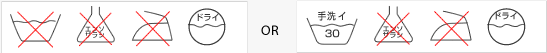

 ランキング
ランキング 新着商品
新着商品 春夏商品
春夏商品